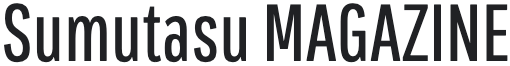親から相続した土地や建物といった不動産には、自身が居住しない空き家であったとしても固定資産税が発生します。
この記事では、空き家の固定資産税の計算方法や固定資産税を抑えるための特例、一定の条件で固定資産税の優遇が受けられなくなる特定空き家について解説します。
空き家には固定資産税が発生する

固定資産税は、不動産を所有していれば自動的に発生するため、たとえ誰も住んでいない空き家の状態であっても、毎年課税されてしまいます。
固定資産税は、毎年4~6月頃になると、その年の1月1日時点での所有者宛てに、支払い通知が届きます。
基本的には、物件の所有者が支払いの義務がありますが、所有者が亡くなっている場合は、不動産の相続人が支払うことになります。また、年の途中で売却した場合は、引き渡し日までの所有期間で売主と買主で支払いを分けるのが一般的です。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、以下の計算式で求められます。
※自治体によっては税率が1.5%や1.6%となることがあります。
固定資産評価額は、土地の広さや立地、築年数などをもとに自治体が算出する値で、3年に1度見直し(評価替え)が行われます。評価額は、実際に売買されるときの価格とは異なり、5~7割程度と低い価格に見積もられることが多いです。実際の評価額は、自治体から届く納税通知書に記載されています。
固定資産税は、不動産がある自治体ごとに算出されます。1つの自治体の中で課税標準額の合計が土地は30万円、建物は20万円未満なら固定資産税はかかりません。
固定資産税が安くなる特例

固定資産税は、一定の条件を満たすことで税額が軽減される特例が設けられています。
土地と建物のそれぞれに特例があるので、別々に解説します。
土地についての特例
人が居住する建物がある住宅用地には、以下のように税金が軽減されます。
|
住宅用地の要件 |
固定資産税の課税標準額 |
| 小規模住宅用地
(200㎡以下の部分) |
×6分の1 |
| 一般住宅用地
(200㎡を超える部分) |
×3分の1 |
例えば、300㎡の住宅用地であれば、200㎡の部分までは固定資産税が6分の1に、残りの100㎡については3分の1となります。
この特例は、住宅用地にのみ適用されるもので、その年の1月1日時点で住宅がない土地には適用されません。
新築の建物についての特例(2024年3月31日まで)
固定資産税は土地と建物それぞれにかけられますが、新築物件の場合は建物部分について固定資産税の軽減措置が受けられます。
以下の条件を満たすと、固定資産税が50%減額となります。この減税の継続期間は、戸建て住宅の場合は3年間、マンションの場合は5年間です。
- 2024年3月31日までに新築された戸建て住宅・マンション
- 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下の場合
また、断熱性能や耐震性などの項目で「長期優良住宅」として認定された新築物件は、戸建て住宅の場合は5年間、マンションの場合は7年間、固定資産税が半額になります。
固定資産税のシミュレーション
ここでは、固定資産税の計算例として、中古住宅を例に挙げて考えてみます。
- 土地の評価額:3,600万円
- 家の評価額:500万円
- 2000年2月に建築(床面積は120㎡以下)
- 税率:1.4%
この不動産は、土地に住居が建っていますので、土地の固定資産税は特例が適用されます。実際に計算すると、以下のようになります。
3,600万円 × 1/6(減税) × 1.4% =8.4万円②建物の固定資産税額
500万円×1.4%=7万円
固定資産税額合計= ①+②=15.4万円
この場合、特例がなければ土地の固定資産税は6倍になります。いかに特例に適用されることが重要か分かります。
特定空き家になると固定資産税の特例対象外に
土地の固定資産税の軽減措置として設けられている特例は、住宅が建っていることが条件になっています。
しかし、2015年に定められた空き家対策特別措置法により、自治体から「特定空き家等」に指定されれば、たとえ住宅が建っていても土地の固定資産税の特例を受けられなくなりました。
特定空き家と指定される条件には以下のようなものがあります。
- 倒壊の恐れがある
- 管理されていなくて景観を損なっている
- 衛生上問題がある
- 周辺環境のために放置しておくことが不適切
古い建物であれば建物部分にはほとんど固定資産税がかからないため、建物の状態に関わらず空き家を残しておいた方が固定資産税の総額が安くなる現状がありました。しかし現在では、状態の悪い空き家を放置すると、固定資産税が大幅に高くなるリスクがあるので、建物部分の管理が必須となっています。
勧告・命令を無視すると過料が科せられる
特定空き家には、ある日突然指定されるのではなく、まず自治体から指導や勧告が来るようになり、それでも対応をしなかった場合に特定空き家に指定されることになります。
特定空き家に指定された場合は、同時に50万円以下の過料が科せられます。
また、周辺に著しく悪影響がある場合、最終的には市町村が特定空き家の所有者に代わって解体することもあります。その際の費用も、もちろん請求されます。
住む予定がない空き家の対処方法は?
固定資産税の優遇があるといっても、活用しない土地や建物に対して、税金を支払い続けるのはできれば避けたいものです。
将来的にその土地に戻って住む予定がないのならば、空き家のまま維持するのではなく何らかの対処を検討した方がよいでしょう。
空き家とその土地の活用方法の選択肢をいくつか紹介します。
- 賃貸物件として貸し出す
- 解体して更地にする
- 売却する
賃貸物件として貸し出す
建物が比較的新しい場合や、リフォームを終えている場合には、空き家を残して賃貸物件として貸し出す方法があります。
この方法は、近い将来その建物に住む予定がある場合にも有効で、自身が住むまでの間、収入が得られますし、人が住むことで建物も傷みにくくもなります。
老朽化が激しく、現状では人が住めないような場合は、リフォームが必須です。しかし、リフォームには大きな費用がかかりますし、リフォームしても確実に入居者が現れるという保証はないため、リスクが大きいでしょう。この対策としては、安い家賃にするかわりにDIY可能な賃貸にする方法も検討してみてください。
解体する
空き家をそのまま活用することが難しい場合には、建物を解体して更地を駐車場にする、更地に新しく賃貸アパートを建てるといった方法があります。
駐車場にすると固定資産税の特例は受けられませんが、立地次第では収益を上げやすくなります。
売却する
遠方に住んでいるなどの理由で、土地の管理が難しい場合には、売却するのがおすすめです。
売却によって不動産を手放してしまえば、その後の固定資産税はかかりません。将来的に自分が住む土地にするという予定がないのであれば、まず売却を検討してみてください。
個人の買い手がなかなか見つからない場合は、業者に直接物件を売却する「買取」という方法も存在します。業者は、リノベーションを前提として物件を買い取るので、状態が悪かったり、築年数が古い物件であっても、簡単に売却できるというメリットがあります。
固定資産税の仕組みを理解して税金を安く
毎年かかる固定資産税には、軽減措置が設けられています。ただし、空き家として放置してしまうと、「特定空き家」に認定されてしまうと、土地部分の課税額が6倍になってしまうので注意が必要です。
持っている不動産が空き家になってしまった場合は、放置するのではなく、何らかの方法で活用する、もしくは潔く売却することをおすすめします。