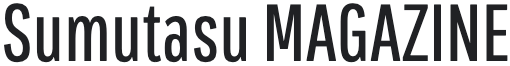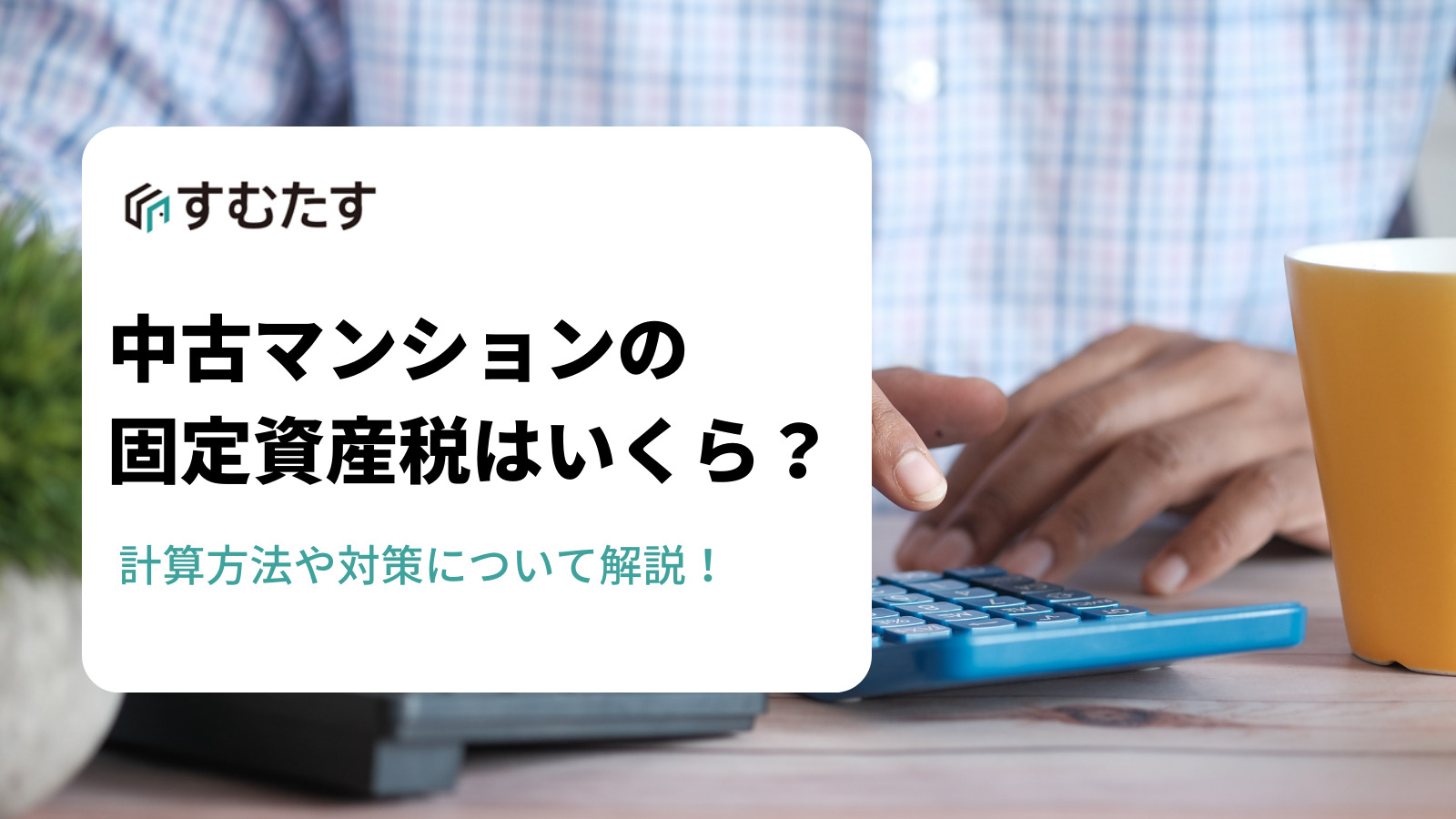固定資産税とは

中古マンションに限らず不動産を所有していると課税対象となる「固定資産税」。そもそも固定資産税とは、個人が所有している土地や物件のような固定資産に対して、市町村より課税が求められる地方税の一種です。
固定資産税は「市町村」に対して課税される地方税ではあるものの、東京23区に限っては区ごとではなく、特例で東京都の都税として徴税されます。
毎年年度始めに固定資産の所有者宛に「固定資産税納付通知書」と呼ばれる書類が送られて来ます。この「固定資産税納付通知書」に従って納税するため、届いたら無くさないよう注意しましょう。納税方法にはふたつ方法があります。
1年間分を一括で支払う方法と、1年間分を4回に分割で支払う方法です。基本的には一括支払いであるものの、窓口で相談すれば分割に応じてもらえるケースも多くあるので、自身の経済状況と相談して決められることが好ましいです。
固定資産税の課税対象となる固定資産税は、毎年1月1日の時点で所有していたものとなります。
納付通知書も、1月1日時点の所有者に対して送られてきます。年の半ばで不動産を売買した場合は、納付通知書の送付先が、不動産の購入者ではなく、前の所有者となります。そのため、固定資産税についての支払いをどうするかは売買契約時に決めておく必要があるでしょう。一般的には日割りで計算してその年における所有期間で平等に負担するという方法が取られています。
固定資産税は、のちのトラブルを避けるためにも個人間での金銭のやりとりが発生するため、慎重に取り扱わなければいけません。
固定資産税はどのように決まる?

固定資産税は、固定資産税評価額と呼ばれる各市町村がそれぞれで定めている不動産の評価額に基づいて算出されます(東京23区は、各区で定めています)。
固定資産税評価額は固定資産が土地であるのか建築物なのかで求め方が異なります。土地の固定資産税評価額は、対象である土地の時価の70%が固定資産税評価額の目安となります。
さらに、この目安に加えて土地の所在エリア、面積、形状、道路との接し方なども詳細に調べられ固定資産税評価額が定められるのです。
また、建築物の固定資産税評価額は、時価ではなく築年数に応じて定められます。請負工事金額の約50~60%が新築の固定資産税評価額の目安です。そのほかにも、建築物の大きさ、間取りなども固定資産税評価額を算出する際のポイントとなります。
中古マンションの固定資産税を求める場合には、築年数が経ってしまっていることから主にマンションの間取りや専有面積を十分に加味して求められるでしょう。
このように、固定資産税は様々なポイントを加味して定められた固定資産税評価額に基づいて算定されています。
また、不動産の所在地によっては固定資産税に加えて都市計画税も発生します。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などに必要な費用の一部を負担する目的で設けられている税金です。自治体によって市街化区域として設定されている区域内にある土地と建物に対して発生します。市街化区域に該当するかどうかは所在地の自治体に確認するのが確実です。
都市計画税の計算方法は以下の式の通りです。
例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地については、年間で3万円の都市計画税が発生します。
税率に関しては自治体によって変動しますが、0.3%が上限です。
固定資産税と都市計画税は同時に納めることになっており、納付通知書も1つにまとまって発行されます。そのため、都市計画税と固定資産税を分けて支払う、固定資産税だけを先に支払うといったことはできません。納税通知書はその年の1月1日時点での所有者に対して、4~6月頃に送付されます。
中古マンションの固定資産税を知る方法

中古マンションの固定資産税を知るためには、まず固定資産税評価額を知る必要があります。固定資産税評価額を知る際、すでに所有している中古マンションなのか、これから中古マンションを購入するのか、どちらの状況なのかによって調べ方が異なります。それぞれどのような方法で固定資産税評価額を調べれば良いのでしょうか。説明していきます。
すでに所有している中古マンションの固定資産税が知りたい場合
すでに中古マンションを所有しており、その中古マンションの固定資産税が知りたいのであれば、年度始めに市町村から送られてくる「納税通知書」を確認しましょう。
納税通知書に添付されている課税明細書の価格の枠に記載されている価格が固定資産税評価額です。
これから購入する中古マンションの固定資産税が知りたい場合
中古マンションを購入しようとしているのであれば、不動産会社の担当者にお願いして売主の方より固定資産税納付通知書の情報を教えてもらえるようにしましょう。自分では調べられないため、不動産屋経由で教えてもらう他ありません。
固定資産税評価額は、毎年同じ書類を見ていては、正確な固定資産税額を知ることはできません。なぜなら、固定資産税評価額は3年に一度見直しが行われているからです。
3年に一度は評価額が変動し、支払う固定資産税も変更になります。常に最新の固定資産税納税通知書を確認するようにしましょう。
中古マンションの固定資産税の計算方法
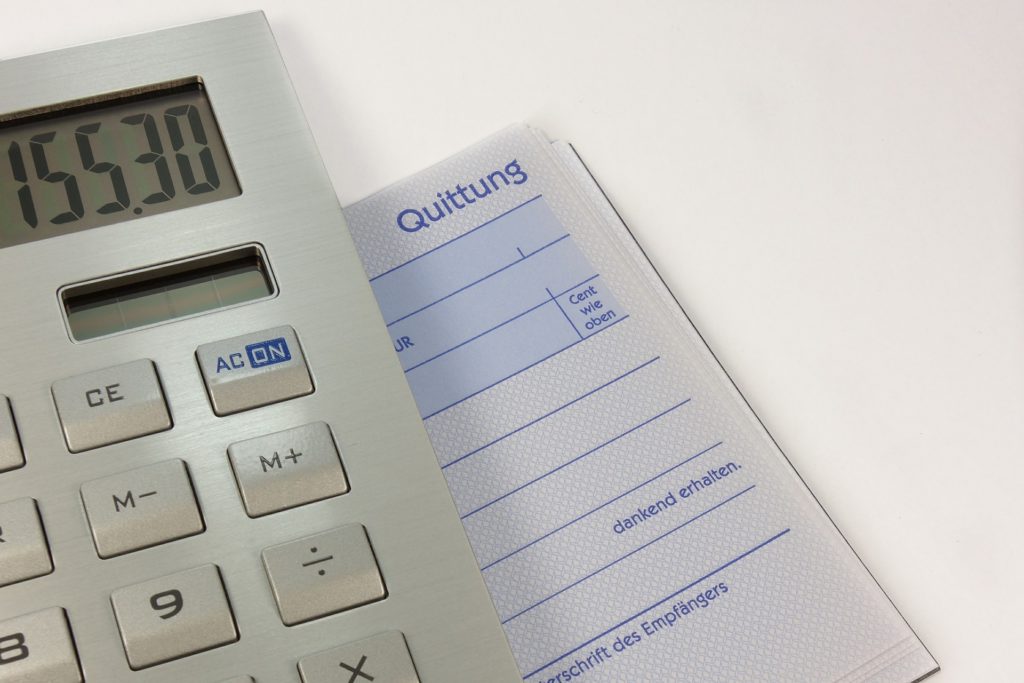
固定資産税と固定資産評価額がどのようなものなのか解説しました。
それでは、実際に固定資産税額を求めるためにはどのような計算をすれば良いのでしょうか。中古マンションに限らず、固定資産税額の算出には、以下のような計算式を用いて算定します。
上記に表記している標準税率(1.4%)は、地方税法の「第2節 固定資産税」で定められている固定資産税の基準税率です。
基準税率は、地方公共団体が自由に決めることができます。しかし、特別な事情がない限りほとんどの自治体で1.4%の標準税率が採用されています。詳しい固定資産税率について知りたいのであれば、念のため各地方公共団体に確認しておきましょう。
固定資産税と都市計画税の計算例
固定資産税評価額が2000万円の土地、1500万円の中古マンション(建物)を所有している場合
固定資産税は
土地が2000万円×税率1.4%=28万円
建物が1500万円×税率1.4%=21万円
合計で49万円です。また、詳しくは後述しますが固定資産税を軽減できる特例もあるので、最大で49万円となります。
都市計画税は
土地が2000万円×税率0.3%=6万円
建物が1500万円×税率0.3%=4.5万円
となり、合計で10.5万円です。これが固定資産税に合わせて発生します。
都市計画税は、土地部分については固定資産税と同様に軽減できる特例が設けられています。
固定資産税は、不動産が所在する自治体ごとに算出されます。1つの自治体の中で課税標準額の合計が土地については30万円、建物については20万円未満なら固定資産税は発生しません。複数の不動産を持っている場合、土地と土地、建物と建物の課税標準額の合計で計算し、土地と建物の合計額で算出するものではない点は注意してください。
例えば、課税標準額が25万円の土地と15万円の建物を同じ自治体内で所有していた場合は、土地・建物ともに固定資産税はかかりません。
しかし、課税標準額が28万円の土地と20万円の土地を同じ自治体の中で所有していれば、合計で30万円を超えるので、固定資産税がかかります。
また、都市計画税については、課税標準額がいくらから発生するというものがなく、市街化区域にある不動産であれば、必ず発生することになります。
中古マンションの固定資産税を減税する方法

固定資産税は、中古マンションでも所有している限り課税され続けてしまうもの。必ず払わなければいけないなら、なるべく減税したいですよね。固定資産税を減税する方法は6つあります。自身の中古マンションに当てはまるものあるかチェックしていきましょう。知っているかいないかで大違いになる可能性もあります。該当するものは活用することをおすすめします。
住宅用地の特例
住宅1戸につき200m2までの小規模住宅用地である場合、固定資産税評価額が×1/6、200㎡を超える一般住宅用地であれば固定資産税評価額が×1/3とかなり軽減できます。
例えば、300㎡の住宅用地であれば、200㎡の部分までは固定資産税が6分の1に、残りの100㎡については3分の1となります。
住宅用地については、都市計画税も軽減できる特例があり、200㎡までの部分は都市計画税が3分の1に、200㎡を超える部分は3分の2になります。
住宅用地とは、一言でいうと住宅が建っている土地のことで、建物がない土地だけの場合は住宅用地の特例は適用できません。また、固定資産税と都市計画税で軽減できる割合が異なる点も注意が必要です。
新築住宅に係る税額の減額措置・認定長期優良住宅に関する特例措置
この2つの措置はどちらも1回だけ適用できるものではなく、新築後5年ないし7年間適用できるものです。新築マンション向けの減税措置ではありますが、中古マンションであっても、適用期間内に購入したものであれば固定資産税の軽減が可能です。それぞれの適用条件と軽減内容を紹介します。
新築住宅に係る税額の減額措置
2026年3月31日までに新築された戸建て住宅・マンションで、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下、居住部分が専有部分の2分の1以上の場合、居住部分の床面積が120㎡までの部分について固定資産税が50%減額となります。
3階建て以上の耐火構造・準耐火構造のマンションの場合は5年間、戸建てや3階建て未満のマンションの場合は3年間、この減税が適用となります。
この減額措置は、名称にもある通り「新築住宅」に対して発生する固定資産税を軽減するものです。住宅は築浅であるほど価値が高く、年月が経つにつれて価値は下がっていくので、新築時が最も固定資産税が高くなるのが一般的です。高い時期の固定資産税を大きく減らすことができる点は大きなメリットだといえます。
認定長期優良住宅に関する特例措置
こちらは条件次第で新築住宅に係る税額の減額措置が延長できるものです。
2026年3月31日までに新築された戸建て住宅・マンションで、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下、居住部分が専有部分の2分の1以上で、かつ、耐震性・耐久性に優れるなど、一定の要件を満たす認定長期優良住宅の場合は、居住部分の床面積が120㎡までの部分について、固定資産税の課税評価額が2分の1に減額される「認定長期優良住宅に関する特例措置」を受けられます。
適用期間は3階建て以上の耐火構造・準耐火構造のマンションの場合は7年間となります。つまり、新築の認定長期優良住宅であれば、住宅部分の固定資産税が2分の1になる期間が、新築住宅に係る税額の減額措置の場合よりも2年間長くできることになります。
省エネ回収促進税制
これは省エネリフォーム税制とも呼ばれるもので、住宅の窓や壁、天井、床などに対し2025年3月31日までに断熱改修工事を行うと、その翌年分の住宅部分に対する固定資産税額の3分の1が減額されるというものです。2014年4月1日以前からある住宅であることが適用条件となっているため、新築住宅に対する減税措置とは併用できません。また、窓への断熱改修工事は必須となっています。
その他の主な適用条件は以下の通りです。
・窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
・断熱改修に係る工事費が60万円を超える
後述する「耐震改修促進税制(耐震基準適合住宅に係る減額)とは併用できません。
また、改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。
その他の詳しい適用条件は以下のリンクからご確認ください。
バリアフリー改修促進税制
「バリアフリー」を目的としたリフォームを行なった場合、リフォームをした翌年1年間、固定資産税の減税制度が適応されます。
こちらは、新築後10年以上を経過した家屋に対して、2026年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行うことで翌年度分の住宅に対する固定資産税の3分の1が減額される特例です。
省エネ回収促進税制と同様に、住宅にかかる固定資産税が軽減できます。
主な適用条件は以下の通りです。
次のいずれかに該当する人が、居住している家屋であること
1.65歳以上の者 (工事が完了した翌年の1月1日時点)
2.要介護認定又は要支援認定を受けている者
3.障がいを持っている者
・新築されてから10年以上が経過した家屋であること
・バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円(税込)
を超えていること
・バリアフリー改修後の床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下であること
・店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
耐震改修促進税制
これは1982年1月1日以前から所在する家屋に対して、2026年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額される制度です。
主な適用条件としては、耐震改修工事に要した費用が、50万円(税込)を超えていることが挙げられます。適用される耐震改修工事の内容など、詳しくは以下のリンクからご確認ください。
長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅は固定資産税の軽減措置が受けられますが、新築・築浅でなくても、リフォームによって長期優良住宅となる場合でも軽減措置の対象となります。
リフォームによって長期優良住宅と認定されれば、翌年度分の固定資産税から3分の2が減額されます。新築の優良住宅の場合は、最大で7年間、住宅に対する固定資産税が2分の1になるものでしたが、リフォームの場合は減額される割合は大きいものの、一度だけの減税となる点には注意が必要です。
主な適用条件は以下の通りです。
・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
・床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下であること
・改修工事を2026年3月31日までに行っていること
その他の詳しい内容については以下のリンクからご確認ください。
固定資産税の減税制度適応中が中古マンションを売却するチャンス

中古マンションの固定資産税を求める方法と、減税方法について紹介していきました。どんな中古マンションでも、持っている限り必ず固定資産税の課税が発生します。自分で住んでいたり、活用していないかったりするのであれば、思い切って売却を考えてみるのもひとつの策です。
とくに、減税制度が適応されて固定資産税が安く住んでいる期間は中古マンションの売却チャンスとも言えます。なぜなら、一年間の間のどこかで譲渡のあったマンションの固定資産税は売主が負担するものの、日割りで買主に固定資産税を請求することができます。
すると、固定資産税の総額は減税のため安くなっていて両者共に負担が少なく済むのに、中古マンションの価値は高くなって高額買取が認められるからです。
減税対策をしたマンションがいくらほどで売れるのかを知りたいのであれば、すむたす売却で査定をしてみてはいかがでしょうか。
独自のAI技術と専門知識で最短1時間で査定価格を提示してもらえます。さらに、最短2日で現金化もできるため、なるべくスピーディーに売却したい方にはとくにおすすめです。
少しでも中古マンションの売却に興味がある方は、ぜひ一度活用してみてはいかがでしょうか。